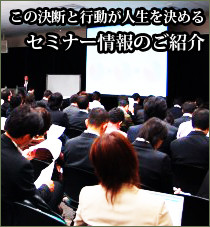連載「実践 事例で考える 不動産コンサルティングの進め方(33)」 ~コンサルタントの役割は「意思決定」~
福田 郁雄 株式会社福田財産コンサル 代表取締役
第34回 ~問題解決技法を身に付けコンサルする~
不動産コンサルタントもコンサルタントの一分野です。コンサルタントは自らの頭を使って問題解決の道筋をつけるのが仕事です。考えに考えぬいて依頼者の対処すべき問題に対して最適案を提示します。問題解決には技法があるので、ある程度技法を身に付ければ誰しもが一定のレベルの問題解決ができるようになります。福田財産がオリジナルで作成した、統合的問題解決技法を初公開します。
1.セールスとコンサルタントの違い

本紙の読者は本業が不動産業である方が多いと思います。本業が調子良くないので、不動産コンサルティングでも始めようかという安易な気持ちでは不動産コンサルティングなどできません。
私はセールスが出来ない人はコンサルティングはできないと思っています。セールスにはコミュニケーション力などのヒューマンスキルが必要ですが、コンサ ルティングはセールス以上にヒューマンスキルが求められるからです。そのうえで、問題解決技法を自由に使いこなせなくてはなりません。最終的には依頼者か ら信頼を得て意思決定をしてもらいます。
意思決定を迫るのはセールスと同じですが、そこまでの道のりの違いがセールスとコンサルの違いです。(図1)
ご存知のようにセールスは欲望に訴え、メリットを強調し、気持ちを盛り上げ、ピーク時に特典や煽りを上手く使いこなし成約へと結びつけます。顧客の気持ちを考えながら、精密な営業ストーリーを構築して、強いマインドで挑みます。これはこれで重要なスキルだと思います。このことを否定する気持ちは毛頭ありません。むしろ、このように頑張っているセールスパーソンを応援したいくらいです。(のうのうとパソコンの前で時間をつぶして働かない本社社員や公務員に腹を立てているのは私だけでしょうか?)
一方、コンサルの場合は顧客の悩みから入ってきます。顧客が何に悩んでいるのか、何をどうしたいのか本質的な部分まで遡り、問題点を特定します。その次にその問題点を解決するための、取り組むべき課題を探りだします。取り組むべき課題を決めたら、様々な角度から検討した対策案を複数比較検討して最も効果的な対策案を選び、顧客に意思決定してもらいます。随分まわりくどいように思えるかも知れませんが、様々な角度からもれなく考えた結果の結論なので納得性があるのです。しかも、一緒にこの作業を顧客と行っていくと、顧客が自ら結論を見出したように思ってくれるので意思決定してもらいやすくなります。
断然、意思決定(成約)する確率はコンサル的アプローチの方が高くなります。ところが、コンサルには二つの落とし穴があります。
一つは最終的に出てきた対策案が自社商品やサービスと違うことになり、せっかく時間かけてコンサルしたのに、商売にならなかったということが起きるのです。であるならば、恰好つけてコンサルするよりは、セールスしておけば大切な顧客を取りこぼすことがなかったということになります。
中には最終的には自社商品に無理やり結論を持っていくというツワモノもいますが、目の肥えた最近の顧客にはかえって不信感を与えてしまうことになりかねません。
もう一つの落とし穴は、下手なコンサルをするとお客様と一緒に悩んでしまって先に進まなくなる点です。問題が拡散して収集が付かなくなり、逆に混乱を招きます。(他責の問題点のみ列挙してマイナス思考に陥るなど)対策案を多く提示しすぎて、かえって意思決定ができなくなるなど、コンサルの技術の未熟さによって、最終地点にまでたどり着かなくという失敗が起きます。
不動産コンサルの推進が難しい所以は、独立系でない限り、自社商品やサービスを使うメリットと対策案が必ずしも一致しないことです。ここでコンフューズを起こすと、結果的にコンサルがセールスの邪魔をしたことになります。
中途半端にコンサル的アプローチを商談に取り入れることによってかえって業績を落とすのはこのためです。
この問題は、経営方針の分野にかかわる問題です。セールス部隊から切り離して、新たにコンサル部隊を創設するなど思い切った対応が必要です。しかもセールス部隊の中からエースを選んでコンサル部隊に投入しなければ、なかなか上手くいきません。エースを抜くとなると、その数字の埋め合わせをどうするかという問題が浮上してきます。選択と集中という観点からすると中途半端なことはしない方が良いということになります。
もう一つのコンサルの進め方に起因する問題は、技能を高めることによって解決が可能です。とりわけ、問題解決技法を身に付け、無意識のレベルまで定着させることが出来たならば、コンサルタントにとってはこれ以上にない財産となります。この技術を身に付けたならば、意思決定までの一連のプロセスの精度が格段に高まり、打率の高いコンサルタントになれるでしょう。
2.コンサルタントに必要な技能
私が活用している問題解決の技法を紹介する前に、全ての分野のコンサルタントに共通する技能を整理しておきます。
そもそもコンサルタントには国家資格など無く、誰でも名乗ればその瞬間にコンサルタントになれます。そのために、コンサルタントの業界はピンからキリまで混在し、詐欺などの社会問題にからむコンサルタントがマスコミを賑わしています。その刷り込みのためか、コンサルタントは皆悪人だと思っている方もいます。(笑) もちろん大半は見識を持ち合わせた方なのですが。
コンサルタントには様々な専門分野がありますが、共通点は、問題解決と企画です。
コンサルを成功させる精度の高い問題解決と成果の上がる企画を実現させためには、下記の五つの能力が必要です。
①カウンセリング力
依頼者の本音や潜在的なニーズをつかむための質問力。
依頼者の考えや気持ちをまず全て受け入れるところから始めます。
決めつけやいきなりの回答は避けなければなりません。
②問題解決能力
本編の主題です。まずは技法を身に付けることから始めます。
多方面から考える発散思考と絞っていく収束思考の繰り返しがポイントです。
問題の本質までたどり着いて解決することにより、同じ問題を発生させません。
③企画力
新しい発想を取り入れ、周りの人を巻き込みながら、企画を推進する力です。
万博やオリンピックや販促イベント、広告などの企画が代表的です。
関係者の共感を呼ぶコンセプトやテーマが成功の鍵となります。
④マネジメント力
問題解決案の実行や企画を実行する時に必要とされる管理能力です。
プロジェクトメンバーの選択やメンバーを動かすしくみづくりも問われます。
もちろんリーダーシップも問われます。
⑤コミュニケーション力
上記の①~④の全てに必要な能力で、ヒューマンスキルとも言われます。
新人から経営者まで全ての階層で必要な能力です。どんなに良い対策案や企画が生まれたとしてもこの力がなければ絵に描いた餅となってしまいます。
分野ごとの知識や経験は確かにコンサルティングに必要ですが、依頼者によって、全て問題が違うので、過去の事例や経験をあてはめるだけでは的外れになってしまいます。ですから、コンサルタントは上記の5つの能力が必須なのです。
例えば資産家の不動産コンサルティングと言っても、持っている財産の額や種類も違うし、場所も違うし、依頼者の年齢や経験や価値観も違うし、相続に対する対応方法も違います。全てオーダーメイドのコンサルティングでなければ、最適な提案は不可能です。かえって、過去の成功体験の先入観によって間違った提案をすることがあるかも知れません。
この5つの能力のうち①が一番大切です。もし、ここで的確な情報が得られなければ、次のステップの問題の本質を見失ってしまうことがあるからです。いわば的外れ、ピント外れな提案となって失敗するからです。
カウンセリング力については、多くの書物やセミナーが開催されているので、興味のある方はそちらで学んでください。
二番目のプロセスは問題解決ですが、この力があるとどんなビジネスでもアドバンテージとなるので是非身に付けていただきたいと思います。
三番目の企画力はまた別の機会にでもご紹介できればと思っています。
四番目のマネジメント力は管理職研修などでお馴染みなので、説明の必要はないでしょう。
それでは以下にその問題解決の手順と手法をご紹介します。
3.統合的問題解決技法
ここで思考スタイルに着目してください。「発散思考」と「収束思考」が交互に書かれています。
「発散思考」とは多面的に考えるということで、もれなく必要情報を集めるということです。抽象的だと分かりにくいので、私は「関心事をとりあえず100出してください。」だとか、「問題点をとりあえず100出してください。」だとか、「アイディアをとりあえず100出してください」等と言います。2個、3個しか出てこない人もいます。こういう人は結構多いです。一般的には20個30個で終わってしまう人がほとんどです。なかなか数を出すというのは大変なことです。6人ぐらいのグループで出し合えば数は増えますし、他人の考えも見えて参考になります。
100個出すと言って80個ぐらいまで行きその先が中々出ないことがあります。実はこの先が大切なのです。その80個ぐらいまでは今までに思い付いたことのある当たり前の話が多く、今までに試してやってみてダメだった情報であったりします。その壁を乗り越えた時点で本当に役立つ情報と出会えるのです。
100個出すとなると日頃からの問題意識や関心がなければ簡単には出てきません。逆に自分の好きな趣味の分野や好みの異性の特徴などは簡単に100個ぐらい出てくるはずです。
実は本も100個ぐらいの見出しがついていることが多いです。何か極めるというとなると、100個ぐらいのテーマについて考えつくしていて、何を質問されてもスラスラ答えられるでしょう。一週間にワンテーマを考えるならば、二年間でプロの領域ということです。
思考を拡散させていくこと、対象のモレを無くすことがポイントです。
「収束思考」とは逆にテーマを絞り込んでいくことです。本質的な問題・課題・解決策に行きつくために情報を統合していくプロセスです。例えば100個のテーマの中から最も大切なテーマを3個から10個選ぶという行為がそれに該当します。100個もテーマがあると何が大切か見えなくなってしまうことがあります。3つだけ選ぶとなると本当に大切なものが浮かび上がってきます。先ほどの本の出版の例えでは、章の決定にあたる部分がこの行為になります。100個のテーマを5章に分け、順番に並べる作業と思ってもらえば分かり易いと思います。
勘違いが多いのは、共通項でまとめてしまうことです。日本ではおなじみのKJ法などが代表的ですが、共通項でまとめても本質は見えて来ません。かえって抽象度を高め曖昧になり本質から外れていってしまいます。むしろ、最も本質を表しているテーマをそのまま、課題にするほうが近道です。例えば本のタイトルですが、100のテーマをまとめるような抽象的なタイトルはインパクトがありません。むしろ、ワンテーマを選びそのままタイトルにしてしまった方が売れるでしょう。これは本質を捉える一言を探り当てたからです。
たとえば「お金の教科書」よりは「金持ち父さん貧乏父さん」のほうが本質を捉えているので購入者に興味を抱かせることができます。
この収束思考はせっかく集めた情報を捨てるという作業でもあります。もったいないなあと思ってはダメです。バッサリと一旦切ることが大切です。また後で、その情報が生きてくることもありますから。
「発散思考」と「収束思考」はフェーズ①の「現状把握」、フェーズ②の「問題形成」、フェーズ③の「対策立案」の全てで使います。
「発散思考」だけでは問題が拡散して収集がつかなくなってしまうので、必ず「収束思考」とセットで用いなくてはなりません。先に「収束思考」で答えを出しておいて、後づけで「発散思考」で情報を付けたすということはやってはいけません。必ず、「発散思考」次に「収束思考」と順を追うことが必要です。
フェーズ①の「現状把握」は何となく困っているといった悩みを「見える化」します。数値や固有名詞で問題点を具体化させることがポイントです。「○○の感じ」から、誰が、何が・どのくらい異常なのかをはっきりさせることです。
当社でまず初めに行う「財産診断」がこのフェーズにあたります。確定申告書、決算書、評価証明、ローン返済表、案内図などをいただいて、財産毎の貸借対照表と損益計算書と収益性と健全性を一覧で示し、不良資産・優良資産を見分けることにしています。
フレームワークとしては、MECE、ロジックツリー、グラフ、表、マトリクスなどを使い、視覚で直観的に判るように「見える化」することがポイントです。(図3)依頼者の感覚的な現状認識と数値で出てきた現状把握には大きなズレがあることに気づいてもらうことができます。
ここではまだ何故といった疑問に踏み込む必要はありません。事実を客観的につかむことが大切です。依頼者からのヒヤリングも同じで、依頼者のおっしゃっていることが事実だと勘違いしないでください。そのようにおっしゃったというのは事実ですが、おっしゃった言葉が問題解決の本質に迫る事実とは異なる場合がほとんどなどで注意が必要です。依頼者からのヒヤリング事項を収束させるためには、MASTかWANTかを区別してもらうと良いでしょう。真のニーズを見極めるために有効です。その時に気を付けるのが、全てMASTだと言ってしまう人がいるということです。物事の優先順位が付けられないのです。こういう場合には、10個のうちMASTは三つ以内にしてくださいと言っておくと良いでしょう。
フェーズ②は「問題形成」です。このフェーズが最も大切です。良く問題解決では課題が見つかった点で80%解決したと言われます。その位、ターゲットとする的確な課題を見つけるということは困難かつ重要なことなのです。何をすれば良いか分からないことが問題であって、何をすれば良いかが分かれば後はやるだけだからです。
ここでのポイントは問題を課題に昇華させることです。問題とは困っている様子を指しているのに対し、課題とは問題を解決するために取り組むべき具体的事項です。問題を課題化させるには、まずは「発散思考」で問題点を列挙していきます。他責でも構いません。広く沢山の問題提起をします。なぜなぜ5回を繰り返し、その問題の問題は何かと広げていくのです。最初は表面上の問題が出てきますが、5回も繰り返すと真の問題点が見えてくるというものです。しかしあまりこれを深堀すると、最後は「何のために生きているのだろうか」と言った哲学や宗教の世界に入ってしまうので、トヨタの生産現場のような限られた状況の中で行うことが良いでしょう。
問題を拡散させたままではまずいので、収束させるために緊急度と重要度を勘案して問題を絞っていきます。色々やらなくてはならないと迷っている方には、この緊急度と重要度を付けてもらうとやるべきことが見えてきます。たまに依頼者に困っていることを列挙してもらい、緊急度を5点満点、重要度を10点満点として点数をつけてもらうこともあります。
最も大切なことは、WHAT、すなわち何をするべきかという戦略を決めることです。コンサルタントの仕事の80%は戦略、すなわち何をすべきかを決めることにあります。
そこで、内部環境である「強み」「弱み」と外部環境である「機会」「脅威」を考えつくして、課題へと収束してくのがSWOT分析です。自己の置かれた立場の強み弱みを分析しながら、競合先の動きや時代・環境の変化のチャンスを捉えるという観点で課題を見つけます。資産家の方であれば、持っている資産を強みとして活かして、底を打ったと思われる時点で、逆張り投資をするというようなことです。
フレームワークのうちのパレート分析は有名です。2割の要因が8割を決めるという法則です。売り上げの8割は2割の得意先が占めているとか、2割の営業マンの実績が全体の8割を稼いでいるとかいうものです。戦略とは選択と集中と言い換えても良いと思いますが、何を止めるかを決めるとやるべきこと(課題)が見えてくるものです。
当社では原則3億円以上の資産家へのコンサルティングに選択と集中しています。そうすると、資産家が望んでいることややるべき課題が明確になってくるからです。
フェーズ③は「対策立案」です。
やるべきこと(課題)が明確になったら、最適案を発散思考で複数出していきます。最初からこれが答えだなんてやってしまうと失敗します。例えば、有効活用でプランを出す時には、手書きのスケッチで構わないので、ゾーニングを3プラン出しておき、その中で最も納得できるゾーニングを依頼者と一緒に決めて前に進むとうまくいきます。プロの建築家が考えたプランということで、いきなり「こちらでいかがですか?」なんてやっていると、最後にふりだしに戻ってしまうこともあります。ここでも依頼者の参画意識がとても大切であることが分かります。問題解決のプロセスを一緒に進めていくことによって、当事者意識が芽生えます。自分で一生懸命考えて、自分で決めたことだからと納得して意思決定ができるのです。プロセスを飛ばしていきなり「これでいかがですか?」と言われても意思決定を先延ばしにされるのがおちです。
フレームワークはブレーンストーミングによるアイディア出しが良く使われます。対策案を決めて実行していく時には、ガントチャートで、日程と項目と担当、予算などを入れて作成すると「もやっ」としていた対策が明確に見えてきます。実行段階ではフローチャートで管理します。
対策案を収束させるポイントは効率性ではなくて、効果性で判断することです。ややもすると、数値の比率で判断しがちですが、それは間違いです。当社でもROA分析という手法で、資産価値に対するネット利益率で良否を判断していますが、最終的な判断は目的に対しての効果性だと考えています。依頼者の最終目的は何なのか、決して効率ではないはずです。ストレスのない生活であったり、煩わしくない生活であったりします。私が過度にレバレッジをかけすぎることなく適度な投資を推奨するのもそのためです。
この最終フェーズのポイントはKFS(キー・ファクター・フォー・サクセス=成功の鍵)です。大前研一が提唱している戦略理論です。成功の鍵が入っているかの確認です。私が思う「成功の鍵」は依頼者の幸せにつながるかどうかです。幸せという言葉が抽象的であるのならば、ニュアンスは異なりますが「満足」と言い換えても良いかも知れません。依頼者の「満足」は安定した収益かもしれません。テナントとの良好な人間関係かもしれません。家族との平和な生活の維持かもしれません。ステータスや周りからの賞賛かもしれません。時にはそれが依頼者の自己満足でしかないかも知れません。いずれにせよ我々コンサルタントの成否は依頼者の「満足」にあるのです。それが問題解決に成功したか失敗したかの判断ということなのです。
4.体で覚えるまで使いこなす
添付の(図2)をご覧ください。これが福田財産コンサルのオリジナルな統合的問題解決技法の全体像です。
大きくはフェーズ①の「現状把握」、フェーズ②の「問題形成」、フェーズ③の「対策立案」に分けて考えます。
必ずこの順番にしたがって、省略することなく進めていってください。
典型的なダメな方の問題解決方法はこの三つのプロセスを省略して、いきなり思いつきの対策案を行います。それでは当然うまくいかないので、また違った思い つきの対策案を行います。手当たり次第思い付いたことを次から次に行います。試行錯誤という聞こえが良いのですが、きちんとした試行をしないと時間とお金 の無駄です。
セールスの現場では、いきなり解決案を提示し、「自社商品やサービスを使えばお客様の問題が解決します。」とやっても構いません。数打てば当たるので、良い見込み客に出会うために、数多くの顧客と出会うことが大切です。
フェーズ①の「現状把握」、フェーズ②の「問題形成」、フェーズ③の「対策立案」なんてやっていては日が暮れてしまいます。

どうしても抽象的な話ですから、分かりづらいかもしれませんが、どんな場合にも応用が利くので問題解決技法をぜひ体得してください。
実は私はこれまで本紙で33回連載していますが、全ての連載においてこの問題解決技法が使われています。本紙を継続購読されている方であるならば、このような視点でもう一度読み返していただくと良いでしょう。
私がこの統合的問題解決技法を創造し、身に付けたのは20代の後半の大手ハウスメーカーの人事部で研修担当を行っていた時です。あらゆる階層のマネジメント研修の企画と運営をやらせていただき、多くの教育コンサルタントや経営コンサルタントと親交を深める機会に恵まれました。そんな中でとりわけ「問題解決力養成講座」と「企画力養成講座」が大好きで、自分なりに多くの本を読み、手法を学び、事例に取り組みました。5年間やったので、自然と問題解決の考え方と技法が身に付きました。そのことが、その後の人生を変えたと言っても言い過ぎではありません。どんな仕事や役割を与えられても「問題解決力」さえあればそれなりにこなせてしまうものだと実感しています。
40代になって、コンサルタントとして独立しましたが、単なる専門の経験や知識だけではなく、応用が利く「問題解決技法」を身に付けていたことが最もコンサルタントとして自立できたのだと思っています。
私は文章を書くことも下手ですし、ましてや人の前で話すこともいまだに苦手です。しかしながら、「問題解決技法」が身についているので、分かり易い言葉で「書いて」「話す」ことがなんとか出来ているんだと思います。
発散思考で数多くの案を出すことも慣れれば大変でありません。フレームワークという道具を使っていけば発散思考をしながら、収束思考でまとめていくこともできます。一見遠回りに見えるようですが、一個一個つめていくことができること、思考の過程を依頼者と共有できて、最後は意思決定につながることを考えれば、大変効率の良い仕事の進め方だと思います。
前回、依頼者は結論を先延ばしにしがちで、せっかく提案書を出しても保留になってしまうことが多いとの話をしましたが、実はこの統合的問題解決技法を順に行っていけば、意思決定につながる確率が飛躍的に高まるということをお知らせしたかったのです。
今、多くの書店でハウツー本が売れていますし、多くの人々がハウツーを求めます。しかし、現実の現場では、全てケースバイケースで応用が利かなければハウツーものは絵に描いた餅となってしまいます。楽をしたいのは分かりますが、自分の頭で考えることを放棄してはならないと思います。
この統合的問題解決技法は企業戦略のような大きな問題から身近な小さな問題まで利用できます。もちろん福田財産コンサルオリジナルの統合的問題解決技法も万能薬ではないと認識しています。世の中の問題解決は技法だけで全て完結するものではありません。
もし、問題解決に決め手があるのですか?と聞かれたならば、「100%依頼者の立場で、もがき苦しんで必死に考えること」とお答えしておきます。
多くの皆さんに思考業務の価値を理解していただけると嬉しいですね。