連載「実践 事例で考える 不動産コンサルティングの進め方(34)」 ~問題解決技法を身に付けコンサルする~
福田 郁雄 株式会社福田財産コンサル 代表取締役
第33回 クロージング技法の紹介
~コンサルタントの役割は「意思決定」~
税理士法人タクトコンサルティングの本郷尚先生は「コンサルタントの仕事は意思決定のお手伝い」とおっしゃっています。どれだけ立派な企画提案書を作成したとしても、意思決定されなければ、絵に描いた餅となってしまいます。そんな経験をお持ちのコンサルタントは多いかと思います。依頼者が納得し、意思決定され行動に結びつき、それがひいては依頼者の満足につながることが最終目的です。
本連載では基本的に一人の依頼者のコンサル事例を時系列にご紹介していますが、今回は特別に「意思決定」を促進させる技法について紹介します。
1.「意思決定」は先送りされるものである
コンサルタントの仕事は、依頼者の現状把握をし、課題を見つけて、最善と思われる対策案を見つけて、プレゼンするのが一連の流れです。しかし、実際に依頼者にとって良い提案が出来たとしても、意思決定されずに保留になるケースが多いことを皆さんも実感していると思います。
立派な提案書を提出しても「ありがとうございました」だけで終わってしまう。企画書作成フィーをもらうだけの仕事なら、そこで終わってしまっても良いですが、それだけでは本来のコンサルタントの仕事ではありません。
「参考になりました」のお言葉だけで、行動に移されないから結果が出ない。これでは、依頼者にとってもコンサルタントにとっても、好ましい状態ではありません。これは多くのコンサルタントに共通の悩みです。私が、多くの事例を通して試行錯誤しながら見つけた、そこを突破する方法論をご紹介します。
そもそもコンサルタントの役割(売り)は何でしょうか?知識の提供でしょうか?問題解決能力でしょうか?経験でしょうか?企画力でしょうか?それぞれ当たらずとも遠からずですが、ズハリ一言で言うと「意思決定のお手伝い」です。
依頼者は漠然とした悩みを抱えており、その悩みを解消していきたいと思っているのですが、何をどのようにすればベストなのか、判断が付かないため、意思決定を先送りしているのです。ある程度、こうすれば良いのかなあと分かっていても自ら意思決定し行動に移すことができないのです。そんな時に相性の合うコンサルタントに出会って、話がスイスイと進んでしまう事も多いのです。
インターネットの普及により、検索するだけで必要な情報が得られるようになりました。もはや知識や情報の切り売りだけでは専門家としての立場はありません。現に弁護士などの専門家は相当危機感を持っているようです。
そんな時代環境の変化の中、チエの部分が重要になっています。つまり、問題解決力、企画力といったコンサルティングの根幹をなす部分が求められています。
しかし、どんなに素晴らしい問題解決案や創造的なアイディアを提供しても、依頼者がそれを受け入れて行動に移さなければ、何も変わりません。問題解決力・企画力は重要ですが、最重要ではないです。
その提案が依頼者の腹に落ち、意思決定され、実行に移されて初めて仕事をしたということになるのです。
そもそも人間は意思決定を避ける傾向があります。先送りするのは本能です。現状にも満足していませんが、現状を変えた時に起きる様々なリスクもイヤなのです。
人間は「意思決定しない」という前提で考えておくべきです。
確かに経営者や企業の幹部のように、日頃から仕事の中で意思決定を行っている人々は比較的得意です。しかし、こと自分の私生活や財産の事になると意思決定できないものです。
ましてや、専業主婦や一般社員では重大な意思決定を行う機会はほとんどないので、相続などの一大事が起きた時は右往左往するばかりです。
実際の現場の中では、ギリギリの状態になって、相談にお越しになる方が多いのが現実です。
例えば、相続の相談であれば親が余命を宣告されてから、不良債権の話では競売になる一か月前から、テナントや借地人との問題がこじれてから、など時間が差し迫ってからの依頼がほとんどです。
ほとんどの方が意思決定を先延ばしにされている現実が理解できると思います。「もっとあなたに早く会えていれば」というフレーズは日常茶飯事です。
では、実際具体的にどのように依頼者に「意思決定」してもらえば良いのでしょうか?
意思決定が出来ない人への対応策は以下の3つです。
① メリット・デメリット比較法
② 時間軸法(目標設定法)
③ 理論・感情W刺激法
それでは、これらの手法を順にご紹介いたします。
2.メリット・デメリット比較法
大半の人はBの「やるデメリット」に目がいくようです。言わば無難な人達です。頭の良い人に多い傾向です。リスクを強調する人です。失敗をしない事が昇進の基準となっている組織で良く起きる現象です。公務員や硬直した企業に多いのではないでしょうか。Bの「やるデメリット」ばかり見ていては何も変わりません。
最終責任のある人、例えば経営者などは、Aの「やるメリット」とBの「やるデメリット」の両方を天秤にかけます。その総量を見て、たとえデメリットがあったとしても、メリットの方が大きければ意思決定し前に進みます。
実はCの「やらないメリット」も大変重要な視点です。とりわけ投資の世界では顕著です。たとえばトレンドが出てくるまで投資を待つという姿勢が重要です。勝間勝代さんがかつて「断る力」という本を執筆され話題になりましたが、Cの「やらないメリット」を強く意識したものです。
Dの「やらないデメリット」は機会損失を見抜く力のことを言います。機会損失とはやらなかった場合の損失です。やった場合の利益や損失は目に見えやすいのですが、やらなかった場合の損失は認識することが困難です。ところが、このやらなかった機会損失はとても大きなボリュームなのです。
セブンイレブンの鈴木敏文氏は単品管理(商品毎に売れ筋と死に筋をタイムリーに把握)するシステムを開発して業績を上げましたが、そのことに満足されていませんでした。本当は並べて置けばもっと売れたモノがあったのかもしれないと疑うのです。機会損失の大切さを良く理解されていたのだと思います。
4つの窓の特徴を説明しましたが、大切なことはこの窓の使い方です。コンサルタントは、依頼者に4つの窓の全体像を見て判断してもらうように誘導しなければなりません。
その窓を見ていく順番が大切です。一般的にはまずAの「やるメリット」から入るでしょう。Aだけグイグイ押しても、すぐにBの「やるデメリット」に目が移りその勢いが増してきます。
そんな時に有効なのが、Dの「やらないデメリット」に目を移してもらう事です。つまり、依頼者に機会損失についてきちんと理解をしてもらうのです。これは、提案を採用しなければ、損をする内容です。人は得することよりも損をしないことにより敏感で重きを置きがちだからです。このDの「やらないデメリット」に納得できれば、その裏返しでもあるAの「やるメリット」に返ってくるのです。そして、Dの「やらないデメリット」の決め台詞は「たった一度の人生です。やって失敗した後悔よりも、やらなかった後悔の方がもっと悔やみますよ」です。やらない後悔に気付いてもらい、保守的な人をアクティブにさせるのです。
上記の決め台詞は実は私自身の信条でもあります。
もう一つのルートは、Aの「やるメリット」からCの「やらないメリット」に目が行く人への対応です。このケースは少ないかも知れませんが、選択と集中が出来る戦略思考を持った優秀な方のケースが該当するかと思います。
この場合も基本は同じです。視点をDの「やらないデメリット」に移してもらうのです。Cの「やらないメリット」とDの「やらないデメリット」の比較検討をしてもらうのです。Dの「やらないデメリット」は見えにくい窓なので、この窓を開いていただいたうえで、検討してもらうのです。その結果、Dの「やらないデメリットの方が大きいと判断したならば、その裏返しでもあるAの「やるメリット」に戻ってくるのです。
もっと総合的に判断したいというのであれば、「A+D」と「B+C」のどちらが総合的に大きいかで判断します。実は、直観で物事を判断する場合においても頭の中では包括的にこれらの判断がされているような気がします。
3. 時間軸法(目標設定法)

一つ目は、メリット・デメリット比較法です。一般的にセールスの現場では、行うメリットのみを強調して、デメリットについてはなるべく触れないようにし ます。競合他社がいれば競合他社がデメリットを伝えてくれるかも知れません。(それも悪口の言い合いで見苦しいものでありますが)
メリットの羅列だけでは、依頼者が自分にとって最適案かどうか分からないので意思決定には至りません。
それに対し、コンサルタントの現場では4つの視点全てで説明します。(図1)4つの視点とは、Aの「やるメリット」、Bの「やるデメリット」、Cの「やらないメリット」、Dの「やらないデメリット」です。
もしもAの「やるメリット」より、Bの「やるデメリット」やCの「やらないメリット」が大きいと判断したならば、その提案を引き下げれば良いだけのことです。もっと優れた提案を再度提案するだけのことです。
二つ目は、時間軸法です。これは、図1のBと通じます。Bは目先の事しか見えていません。投資をする場合、ほとんど目先にはデメリットがあります。手間がかかる、費用や税金がかかる等です。これらは誰にでも分かるデメリットです。それに対して、メリットである将来の利益は見えにくいものです。将来の事ですから、不可実性が高いと言った方が良いかも知れません。
ソ目先のデメリットだけを気にして、将来の大きなメリットを機会損失するのです。
そもそも投資とは目先で損して、将来大きなリターンを得るものなのです。その事自体を投資というのです。

具体的方法を申し上げましょう。(図2)
まずは依頼者の頭の中に時間軸を作ってもらうのです。過去を見て、将来をイメージしてもらい、今何をすべきかを考えてもらいます。
例えは土地の価格を過去から時系列で見てもらいます。20数年前から下落基調が続いています。この先も、人口減少や経済のグローバル化の進展でデフレの 進行が予想されます。当然、地価は下がり続けジリ貧状態となっていくイメージが出来上がります。であるならば、キャッシュを生む資産に組み換え、キャッ
シュリッチになった方が賢明である事に気が付きます。ならば今、遊んでいる土地を売却して、都心の収益不動産に組み換えインカムを得よう。と判断に繋がり ます。
この手法は特に問題が顕在化してない時に有効です。今は問題が表面化していないのですが、水面下で進んでいるようなジリ貧状態のケースです。「ゆでガエル現象」と言っても良いでしょう。
こんなケースでは、将来の目標を明確にすると、意思決定と行動に繋がります。
将来目標を設定すると現状とのギャップが明確になります。今のままでは、その目標を達成することは出来ません。目標と現状の差がそのまま解決すべき課題になります。
目標は具体的であればある程良いです。例えば、「10年以内に相続税を現金で払えるだけのキャッシュを得る」などは分かり易い目標です。
「毎月100万円の自由に使えるお金が得られるようにする」でも良いでしょう。100万円自由に使えれば、値札を見ながら買い物しなくて済みますよね。
「20年以内にビリオネアーになって、最後は恵まれない人に大半を寄付する」というようなアメリカンドリームでも良いでしょう。
明確な目標が決まると、それを達成するための最短の方策を一生懸命考え、行動に移すということに繋がります。
換言すれば、投資の発想を身につけていただくということです。目先の損得より、将来の大きな利益の為に時間やお金を使うということです。
「未来志向」と言っても良いかも知れません。
ジムに行くとのは目先は苦しいけど、将来的には健康というかけがえのない利益が教授できます。
知り合いのNさんですが、今年の夏休みはリゾートでは無く、1週間の語学短期留学に行ってきました。確かに1日11時間のレッスンと寮生活は大変でした が、視野が広がったり、英語に慣れたり、人脈が広がったりと将来の大きな利益につながるのではと自分への投資という意味合いで行ってきたのです。
目先の楽しみより、目先の苦労と将来の大きな楽しみを優先させるのです。目先の楽しみに費やすのは消費、将来の利益に費やすのは投資です。投資と投機の違 いが認識されず、日本では投資を良い意味では使われないのですが、投資マインドは最も大切な思考の一つだと思っています。
過去を見て、将来を見て、今すべき事を決定する。優れた経営者の思考方法です。投資家や経営者が自然にやっているこれらの思考方法を依頼者にも持ってもらえるように働きかけます。
資産を上手に活かして、お金を得て、世の中に役立つことに投資をしていく。
その投資がさらにお金を生み、さらに世の中に役立つことに投資していく。投資の好循環を生むような目標設定が理想です。
4. 理論・感情W刺激法
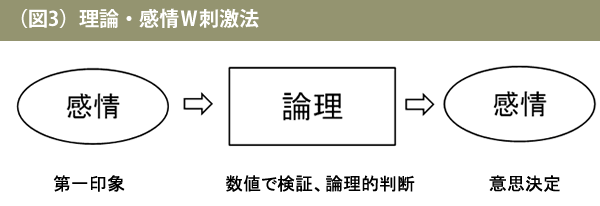
三番目は、理論・感情W刺激法です。現場ではこの事が一番ないがしろにされているにもかかわらず、最も重要な事項ではないかと思います。
人の意思決定は論理的でなければならないと思われていますが、案外それはウソで、実際は感情で物事を決定している事の方が多いようです。
物事を意思決定する時の、人の反応には順番があります(図3)。まず、第一印象での反応です。直観でこれは良い。面白そう。何かワクワクドキドキしそう。などといった「感情」です。右脳が働きます。
その次は左脳が働きます。そのことに関する、情報を集めて、数値で検証し、論理的な判断をします。コンサルタントや専門家の一番得意な分野です。この論理的な検証を省いて意思決定することは大変危険です。思いつきやイメージで判断して失敗する人が多いことからもお分かりになるかと思います。
最後の段階では再び右脳的な感情で判断します。例えば人は「好きか嫌いか」で判断するようなところがあります。経営者であれば「理念」や「夢」につながる話かで決断します。もっと卑近な例で言えば、バーゲンセール中に今買わなければ損だからというのもある意味感情で判断しているではないでしょうか?
私もコンサル中に感じるのが、ネット利回りなどの数値で良かれと思ってお薦めした収益不動産にもかかわらず、決定した理由を聞くと、「見栄えが良かった」「ブランド立地にあった」などと数値では無く、感性やイメージの部分で判断されていることが分かり、少しガッカリすることもあります。
このように、依頼者に決断してもらうためには、理屈、・理論だけではなく、感情だけでもなく、両方相互に刺激しなければいけません。
専門家の中には、理論、知識、分析が得意でその分野だけを突っ走ってしまって、依頼者との溝を広げている方も多いように思います。この事は最も注意しなくてはならない事です。人間は感情で判断する生き物であるという認識が必要です。
資産の組み換えを例に取ってお話ししましょう。もはや「資産の組み換え」という活用方法はポピュラーになり、有効活用のメニューとなっています。資産家の方も一度は聞いた事があるでしょう。確かにすぐれた活用方法だとも認識してくれます。賃貸需要のない場所で無理やり賃貸ビルを建築して苦労するよりも、その土地を売却して、現金化しそのお金で需要の旺盛な場所で収益不動産を購入する。理屈で言えば誰にでも分かる話で、そのことに対する反論の余地はありません。
ところが、実際に実行する人は少数派です。(当社のコンサルを受ける人は多数派ですが)
なぜなら、組み換えというのは、目先に失うものが多いからです。先祖伝来の土地を売る。小さいころから育った思い出の自宅を売却するなど。失うものが大きいので、それ以上に大きい将来の利益にまで、思いが行かないのです。
さらに突っ込んで言えば、「面子」が許さないのです。「あいつはとうとう土地を売ってしまったよ。何かあるんじゃないか」というような近所の噂がとても気になるのです。日本においてはいまだ村社会的な意識で生活をされている方が多く、気持ちは良くわかります。ところが、そこで終わってしまっては前に進みません。こんな時には、見地見学をお薦めします。将来組み換えたイメージが明確になります。組み換えて得られる家賃収入の使い方も、イメージが膨らめばもっと意思決定が進みやすくなります。
5.意思決定を二人で分担することも

実はこんな時にあっさり、「前に進みましょう」と言ってくれるのが奥様やお母様であったりします。女性の方が度胸があるのでしょうか?確かにご主人の方が 社会とのつながりが深く、世間の噂を気にすることも多いでしょう。ところが本質的に女性の方が的確な判断をする資質を持っているのではないかと思う事があ ります。
(図4)をご覧ください。①メリット・デメリット法と③理論・感情W刺激論を男脳、女脳というカテゴリーで応用した図表です。男脳の「強み」は論理的で客 観的にものを見ることができる事です。一方「弱み」は空想的というか、面子にこだわるというか、どこか見栄っ張りな部分が顔を出します。
女脳の方はと言えば、「強み」は現実的なところです。実を取る事ができると言っても良いでしょう。「弱み」は感情や主観で判断してしまうことです。好き嫌 いなどの自分の気持ちが優先される点です。男脳の論理的な「強み」と女脳の感情的な「弱み」はお互いに補完されます。一方、男脳の空想的な「弱み」と女脳
の現実的な「強み」もお互いを補完されます。夫婦で結論を出すというのは、ある意味うまく機能しているのだなあと感じる事が多いです。
会社の中でも意思決定する場合には男脳を持った社長と女脳を持った専務がバランス取って意思決定するとうまくいくのでしょう。
資産の組み換えの意思決定の場面においても、男脳の「強み」で実行すると判断し、男脳の「弱み」で躊躇し、女脳の「強み」で最終決定を行うというシーンが展開されているのです。
Aさんの奥さんは言いました。「お父さん、人の噂なんて半年もしたら何もなかったように消えていますよ」「今、何をすべきかわかっていますよね。」と。




